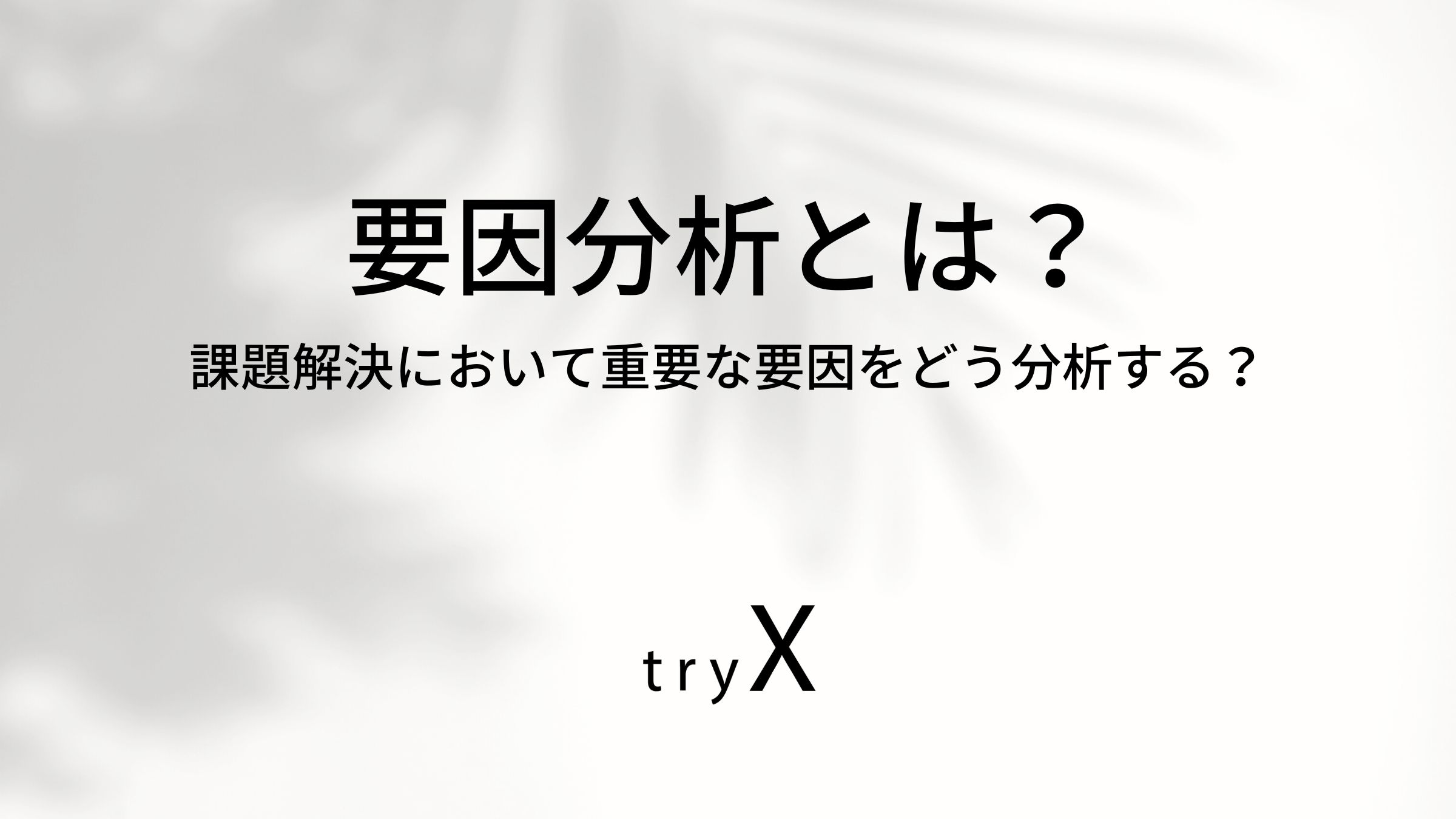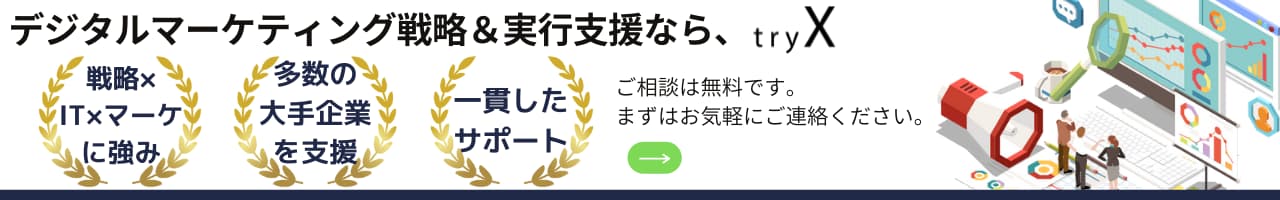新規事業の推進には、課題解決が重要なプロセスです。その課題解決を効率的に進めるために必要になってくるのが「要因分析」です。要因分析とは、問題の発生要因を抽出し、それぞれの要因が問題にどの程度影響を及ぼしているかを分析する手法です。この記事では、その重要性と定義について解説し、新規事業推進を担当している方に向け、具体的な活用方法をご紹介します。
要因分析は問題解決のステップの一つであり、問題の原因を特定するのに重要な工程です。要因分析を実施することで、問題の本質を理解し、それぞれの要因が問題に及ぼす影響度を把握することが可能になります。これにより、問題解決のための具体的な解決策を検討する時に、何に焦点を当て、何を優先すべきかを判断できるようになるのです。
要因分析を行う時に大切なことの一つは、「部分的な要素ではなく、全体を理解しようとする」ことです。問題を解決するためには、一つ一つの要素を切り離して考えるのではなく、それらがどのように全体として機能し、問題を生じさせているのかを理解することが必要です。
具体的な活用方法は、次の章で詳しくご紹介しますが、基本的には課題や問題が発生した際にまずその背景や要因をリストアップし、それらを要因分析するという流れになります。その上で、影響度の大きい要素から優先的に問題解決に取り組むべきか、または低い要素から解決を試みるべきか、といった判断をしていきます。
このような要因分析の活用は、新規事業の推進を行う上で欠かせないものです。新規事業の立ち上げや推進には、多くの課題や問題がつきものです。その中で、効率よく問題解決を進めるためには、問題の要因を的確に分析し、優先度を決定することが必要となります。
目次
1:要因分析とは何か
要因分析とは、データのパターンを解き明かし、そのデータを構成する要因を明らかにする分析手法です。大量のデータの中から重要な情報を見つけ出し、その情報を活用するためのツールとして使われています。
ではなぜ、要因分析は課題解決において重要な役割を果たすのでしょうか?以下では、次のポイントについて解説していきます。
- 1-1: 要因分析の定義と手順
- 1-2: 要因分析を用いて課題解決を進めるメリット
1-1: 要因分析の定義
ビジネスを進める上で問題や課題が発生した場合、その課題を本質的に解決するために、背後に存在する要因を詳しく理解することが重要となります。その際に用いられる分析手法が「要因分析」です。要因分析とは、問題や課題の背後に潜んでいる要因を見つけ出し、整理し、評価することで、問題を解決するための対策を立てるために行われる手法を指します。
要因分析の活用によって、問題や課題の本質を理解しやすくなるのはもちろん、その解決策を検討する際の方向性を見定めることが可能になります。
具体的な要因分析の手法としては、フィッシュボーン図や5W1Hなどがあります。フィッシュボーン図は、問題の要因を「人・手法・材料・機械・測定・環境」の6つのカテゴリーに分けて分析する方法、5W1Hは、「何を(What)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「どのように(How)」「なぜ(Why)」という視点で要因を見つけ出す方法です。
また、要因分析を行う際には、すべての問題が複数の要因から生じているという観点を持つことが重要です。問題の発生要因は一つだけではなく、複数の要因が絡み合って生じている場合がほとんどのためその全ての要因を把握し、整理することで、本質的な問題解決につながるのです。
1-2: 課題解決における要因分析の役割
要因分析は、課題解決の過程で非常に重要な役割を果たします。ここからは、その具体的な役割について詳しく解説していきます。
まず第一に、要因分析は課題の原因を明確に定義する役割があります。課題には様々な原因が絡み合っていることが多く、個々の要因を明確にすることで、根本的な解決策を見つけ出す手助けとなるのです。
第二に、課題の優先順位を決める役割があります。すべての原因を一度に解決することは難しいため、要素分析を通じて影響度の大きなファクターを特定し、最も解決が急務となる課題を特定します。
そして最後に、解決策の有効性を評価するために重要な役割を果たします。要因分析を通じて、特定の解決策が課題の根本的な原因に対してどれだけ有効であるのかを評価することが可能となります。
以上のように要因分析は課題解決において非常に重要な役割を果たします。以下では、これらの役割がどのように課題解決に繋がっていくのか、その手法について詳しく見ていきます。
< 株式会社tryXのコンサルティング支援サービスのご紹介 >
新規事業で何かお手伝い出来ることはありませんか?
株式会社tryXでは、アイデアの創出から実行支援まで、ワンストップで伴走したコンサルティングサービスを提供致します。
弊社のコンサルティングサービスは、 数年間の長期にわたるご支援実績が豊富な点が特徴的で、東証スタンダード上場企業様からも多くの信頼を獲得しております。もちろん中小企業様もご支援させて頂いております。
まずは無料でご相談してみてください。
株式会社tryXの新規事業コンサルティング支援について詳しく >
株式会社tryXでは、データ主導での意思決定を支援する、デジタルマーケティングコンサルティング支援を行っております。
戦略策定から実行支援までワンストップで、伴走型でご支援するため、限られた資源でマーケティング効果を最大化することが出来ます。これらの成果は累積で積み上がり、加速度的に事業を成長させることが出来ます。
まずは無料でご相談してみてください。
2: どのように要因分析を行うか
要因分析を行うことで、問題を解決したり、有益な情報を抽出することができるのは上で述べた通りですが、どのように行うのでしょうか?ここからは、要因分析の具体的なやり方と、その分析結果をどのように解釈し活用するかについて説明します。
- 2-1: 要因分析の具体的な手法
- 2-2: 分析結果の解読方法
- 2-3: 分析結果の活用方法
2-1: 要因分析の具体的な手法
要因分析を効率的かつ効果的に行う手法は多種多様ですが、ここでは、五つの具体的手法について紹介します。
1. ブレインストーミング
問題解決に必要な要因を探る初期段階で有効なのがブレインストーミングです。チームで行うことで多角的な視点から要素の洗い出しをすることができます。その結果をまとめて要因のリストとします。
2. 5W1H
次に、それぞれの要因に対し、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)を問うことで、要因の背後にあるさらなる要素を見つけていきます。ここでは、あくまで仮説としての要因を出していくことが重要で、具体的な事実関係を確認する段階ではありません。
3. フィッシュボーン図
出てきた要因をさらに分析するために、フィッシュボーン図を用いることがあります。問題の要因を「人間」「方法」「機械」「物質」「測定」「環境」などの規準に分類し、細分化していきます。これにより、要因が見えにくい問題も明確にすることができます。
4. 要因間の関係性の分析
要因のリストを作ったら、要因間の関係性を分析することが有効です。それぞれの要因がどのように関連し、問題にどのように影響しているかを調べるためには、システムダイアグラムのようなツールを用いることがあります。
5. データによる検証
以上の方法で出てきた要因が本当に問題解決の鍵となる要因であるかを確かめるために、データによる検証が必要です。具体的な事実関係を明らかにするためには、統計的な方法を用いて検証を行うことが一般的です。
2-2: 分析結果の解読方法
分析の結果が出ても、それをどのようにとらえ、どのように活用すればよいのかが分からなければ意味がありません。以下では、具体的な解読方法を説明します。
まず、要因分析の結果は因子負荷量の形で出力されます。因子負荷量は、各要素がどの因子と関連が深いのかを示し、絶対値が大きければ大きいほどその因子と強い関連があると解釈します。数値自体にはそれほど意味はありませんが、要素と因子との関連性の強さを示すのに用いられます。
次に、因子負荷量が出てきたら因子の意味解釈を行います。一般的には、因子負荷量が高い要素が多い因子を強く意識するとよいでしょう。因子の意味解釈は絶対的なものではなく、一般的な解釈の一例となります。
解釈が終わったら、各因子が課題解決にどのように関わっているのかを考えます。ここでの因子の関連性の観察が大切になります。各因子が、どのように組織の課題と結びつくのか、どのように改善に繋げられるのかを考えると、より有効な活用が可能となります。
- 因子負荷量の認識: 因子負荷量は各要素と因子との関連性を示す。数値が大きいほど関連性が強い。
- 因子の意味解釈: 因子負荷量が高い要素の多い因子を強く意識する。それぞれの因子が何を意味するのかを解釈する。
- 因子の関連性の観察: 因子が課題解決にどのように関わっているのかを観察し、それをどのように活用するかを考える。
解読は、これらを一つ一つ丁寧に行い、各因子の関連性を解明することが大切です。そうすることで要因分析の結果を深く理解し、活用することが可能となります。
2-3: 分析結果の活用方法
要因分析の結果を、活用する方法には具体的にどんなものがあるのでしょうか。以下では、要因分析の結果を活用する3つの具体的なステップを紹介します。これを実施することで、課題解決に応用するための基盤を構築できるはずです
Step1: 優先度の決定
すべての要因を一度に解決することは現実的ではないため、まずは何から手をつけるべきかを考え、優先度を決定します。解決すべき要因を洗い出し、それぞれの要因が課題に与える影響度や解決の困難度を考慮し、優先度をつけます。
Step2: 課題解決のアクションプラン作成
優先度が決まったら、それぞれの要因をどのように解決していくかを具体的にしたアクションプランを作成します。課題解決に向けた具体的なステップ、それを実現するためのリソース、期限などを決定し、計画を立てます。
Step3: フィードバックループの構築
課題解決のプロセスは決して一方通行ではありません。アクションプランを実行した結果を定期的に評価し、それに基づいてプランを更新するフィードバックループを構築します。これにより、課題解決のプロセスを継続的に改善し、より効果的な結果を得ることが可能になります。
これらを行うことで、要因分析が単なる分析手法に留まらず、課題解決を効率的に推進するためのプロセス設計に役立つことが理解いただけたかと思います。ただし、これらのステップを踏むためには、要因分析という手法を理解し、正しく実施することが前提となります。
3: 事例による要因分析の活用方法
要因分析は抽象的な概念であるため、具体的な事例を通じて理解を深めることは非常に有効です。特に、成功事例の分析はその要因を具体的に理解し、課題解決に活用するための有用なヒントを得られる機会となります。
ではなぜ、事例が要因分析の理解に役立つのでしょうか?以下では、次のポイントについて解説していきます。
- 3-1: 成功事例の紹介
- 3-2: 事例から見る要因分析の重要性
- 3-3: 課題解決に繋がる要因分析の活用提案
3-1: 成功事例の紹介
要因分析の有効性を具体的に理解するためには、実際の成功事例を知ることが有効です。ここでは、新規事業の立ち上げに成功した企業の事例を紹介します。
事例として挙げるのは、AI技術を活用した新規事業開発に成功したIT企業です。この企業が要因分析を行ったのは技術の独自性、市場のニーズ、競合企業との差別化、そして優秀な人材の獲得の4つです。これらの要素はすべて、新たなAI技術事業化成功への鍵となる要因でした。
この企業は、まず初めに技術の独自性を要因分析の対象としました。既存のAI技術との比較、特許出願の状況、顧客からのフィードバックなどを基に、独自性を確立しました。
次に市場のニーズを分析しました。ユーザー調査を行い、どのようなニーズが存在するのか、現行の技術では解決できない問題は何かを洗い出しました。このニーズを満たすための具体的な解決策をAI技術の特性を活かして開発したのです。
さらに、要因分析により競合他社との差別化にも成功しました。他社の事業戦略やAI技術の特性を分析し、自社の強みである「独自性」を活かせるポイントを明確にしました。
最後に、要因分析を活用して人材確保にも成功したのです。新規事業を推進するためには人材が不可欠であり、採用を成功させるためには、何を求め、何を提供するのかを明確にすることが必要です。この企業は、自社の強みやビジョンを明確にし、それを求める人材に訴える方法をとりました。
この事例から、要因分析が新規事業立ち上げの各フェーズでどのように活用され、どのような実績をもたらしたのかがわかります。各ステップで要因分析を行うことで、課題を明確にし、それに対する解決策を具体的に導き出すことができたというわけです。要点を整理すると以下のようになります。
- 技術の独自性分析:既存のAI技術との比較や特許申請、顧客のフィードバックから独自性を確認。
- 市場ニーズの分析:ユーザー調査、現行の技術では解決できない問題の洗い出しと有効な解決策の開発。
- 競合企業との差別化分析:競合企業の分析により自社の強みを明確化し、それを活かす方向性の発見。
- 人材確保の要因分析:自社のビジョンや強みを明確にし、それに応じた人材確保の成功。
以上の要因分析により、新規事業立ち上げとそれに伴う難題への解決策を具現化し、事業化に成功しました。
3-2: 事例から見る要因分析の重要性
新規事業の成功・失敗には様々な要因が影響を与えていると言われています。しかし、それぞれの要因がどの程度の影響を及ぼしているのか、それを具体的に知る方法はなかなか見つからないものです。ここでは、具体的な事例を通じて、要因分析の重要性について理解していきましょう。
事例1: e-コマースの失敗
ある新進のe-コマース企業が、新規事業を立ち上げました。しかし、売上は想像以下、結果失敗に終わりました。具体的な要因は分析せずに、単に市場規模が小さすぎた、競合が強すぎたと結論付けられました。
しかし、後に要因分析を行ったところ、競合との差別化に失敗し、UXが不十分だったことが判明しました。他にも、配送体制の不備、PR戦略の欠如などが失敗の要因として見つかったのです。
事例2: スマートフォンアプリの成功
一方で、別のゲームアプリ開発企業は新規事業を成功させました。事業初動から要因分析を導入しており、市場のニーズと競合分析、マーケティング戦略、開発者のスキルと経験など、成功のためのキーファクターを明確に分析しました。分析により明らかになった要因に基づいて戦略を立て、それが結果的に成功に結びつきました。
これらの事例を通じて、顕在的な成功・失敗の背後にはさまざまな要因が絡んでいることがおわかりいただけたかと思います。それらを的確に把握し、分析・解釈し、改善・強化するためには、要因分析が必要不可欠なのです
3-3: 課題解決に繋がる要因分析の活用提案
要因分析が課題解決にどのように役立つのかを知るためには、要因分析のもつ可能性を深く理解することが必要で、それには具体的な活用法を知ることが大切です。以下では、要因分析を用いた課題解決のアプローチを3つ提案します。
課題発生の背後要因を特定する
要因分析を活用することで、課題が発生した理由や背後にある要因を特定することが可能になります。具体的には、予期せぬ業績不振や生産性の低下など、企業が直面する多様な課題の背後にある要因を解明することで、問題解決のための最適なアクションプランを策定できます。
要因と対策をマッチングする
要因分析を行うことで、特定した要因への具体的な対策を立案することが可能になります。対策の具体例としては、業績不振に繋がる要因として売り上げ低下を特定した場合、その対策として販売戦略の見直しや新たなマーケティング活動を提案するなどが挙げられます。
業務プロセスの最適化を図る
要因分析により、業務フローやプロセスに潜在的な課題や改善点を見つけることが可能となります。例えば、プロジェクトが遅延しやすい要因として、業務フローに無駄が多いことを特定した場合、業務プロセスの最適化を通じて改善を推進することが可能です。
ここでの推奨する3つのアプローチはあくまで一例であり、要因分析の活用法は企業の状況や課題によって多様です。重要なのは、企業特有の課題を解決するための適切な要因分析の方式を見極め、実践することです。要因分析により問題の本質を理解し、最適な解決策を立案し実行していくことが、課題解決を実現する第一歩となります。
まとめ: 要因分析の可能性と課題解決への活用について
今回のコラムでは、「要因分析」についてご紹介してきました。課題解決において、「要因分析」は、ビジネス上の複雑な問題を構造的に理解する手法として有効です。各要因が全体に及ぼす影響や相互の関係性をはっきりさせることで、問題解決のためのアクションを考えることができるためです。
例えば、新規事業の推進においてありがちな問題を考えてみましょう。プロジェクトが遅延してしまう、新しい市場の開拓がうまく進んでいない、といった問題に直面したとき、それらの状況の背後にある様々な要因を特定し分析することで、解決に向けた一歩を踏み出すことができるはずです。
また、要因分析は新規事業の成功要因や市場のトレンド、顧客ニーズなどを把握し、事業推進を最大化するためのツールともなります。
要因分析の理解と活用が、より良い事業推進と結果に繋がるでしょう。
< 株式会社tryXのコンサルティング支援サービスのご紹介 >
新規事業で何かお手伝い出来ることはありませんか?
株式会社tryXでは、アイデアの創出から実行支援まで、ワンストップで伴走したコンサルティングサービスを提供致します。
弊社のコンサルティングサービスは、 数年間の長期にわたるご支援実績が豊富な点が特徴的で、東証スタンダード上場企業様からも多くの信頼を獲得しております。もちろん中小企業様もご支援させて頂いております。
まずは無料でご相談してみてください。
株式会社tryXの新規事業コンサルティング支援について詳しく >
株式会社tryXでは、データ主導での意思決定を支援する、デジタルマーケティングコンサルティング支援を行っております。
戦略策定から実行支援までワンストップで、伴走型でご支援するため、限られた資源でマーケティング効果を最大化することが出来ます。これらの成果は累積で積み上がり、加速度的に事業を成長させることが出来ます。
まずは無料でご相談してみてください。